
「介護認定 基準って、思ってたより厳しくない?」
あなたも、そう感じたことがあるかもしれません。 親の介護が必要だと感じて、 いざ申請してみたのに、結果は“非該当”や“要支援1”。 「いや、どう見ても大変なんだけど…」というあの悔しさ。 実は、介護認定 基準には、私たちが知らない“落とし穴”が存在します。
でも安心してください。 この記事では、その見落とされがちな介護認定 基準の チェックポイントや、よくある“判定ミス”の原因、 そして対策方法までしっかり解説します。
あなたの家族が本当に必要な支援を受けられるよう、 一緒に介護認定 基準のカラクリを見抜いていきましょう!
Contents
そもそも介護認定 基準ってどう決まるの?
介護認定 基準は、市区町村が実施する制度で、 「要支援」「要介護」などの区分を決定するためのものです。
ポイントは大きく2段階あります。
- コンピュータ判定(一次判定)
- 審査会による判定(二次判定)
これらの判定には、訪問調査や医師の意見書が用いられます。 ただし、ここに“あるズレ”が生じることで、 本来受けられるはずの認定から外れてしまうケースもあるのです。
見落としがちな介護認定 基準の“落とし穴”とは?
本人が元気そうに見える瞬間に要注意
訪問調査の際、本人が急に元気になることがあります。 調査員の前では気を張ってしっかり答えようとするため、 「問題なし」と判断されがちです。
介護認定 基準では、「普段の生活の困難さ」が正しく伝わらなければ、 正確な判定にはつながりません。
対策:
・普段の様子を写真や動画で記録する
・本人が言いにくいことは、家族がしっかり伝える
認知症の兆候が“軽視”されることもある
軽度の認知症は、介護認定 基準で十分に反映されないことがあります。
「日付や人の名前を忘れる」「同じ話を繰り返す」といった症状は、 “まだ大丈夫”と見なされることが多いのです。
対策:
・医師の意見書にしっかり症状を書いてもらう
・日常の困りごとをメモしておく
介護者の負担が考慮されない場合がある
介護認定 基準は、本人の状態を基本にしていますが、 実際の介護は家族の負担によって成り立っていることが多いです。
- 介護者が高齢や病気である
- 共働きで日中は面倒を見られない
こうした状況が軽視されると、「要介護ではない」と判断されることも。
対策:
・面接時に介護の実態を丁寧に説明する
・可能ならケアマネや第三者の意見も伝える
正しく伝えれば変わる!介護認定 基準を突破するコツ
訪問調査では、どれだけ“正しく伝えられるか”が重要です。
- 事前にチェックリストを作成する
- 質問に備えて答えを整理しておく
- できるだけ“普段の様子”を具体的に伝える
医師の意見書も大切な役割を果たします。
形式的に書かれてしまうと、 必要な支援が十分に伝わらず、軽い判定になる恐れがあります。
対策:
医師に日常の様子や困りごとをきちんと伝え、具体的に記載してもらいましょう。
ダメだった場合の“再申請”も検討しよう
「非該当だったから」と諦める必要はありません。 介護認定 基準に納得できない場合、 一定期間をあけて再申請が可能です。
状態の悪化やサポート体制の変化などがあれば、再度チャレンジしてみましょう。
まとめ|介護認定 基準の“落とし穴”を見抜こう
介護認定 基準は一見公正に見えますが、 実際は細かな要因で「対象外」とされることもあります。
だからこそ、
・本人の普段の状態を正確に伝える
・認知症の兆候を具体的に説明する
・介護者の負担をしっかりアピールする
これらのポイントを意識するだけで、 評価が大きく変わるでしょう。
もし「ウチの親は対象外だった」と感じても、 それはあなたの努力不足ではありません。 制度の“伝え方勝負”という側面が強いのです。
次回の申請では、きっと良い結果が得られます。 一緒に、納得できる支援を受ける準備を進めましょう。
あなたとご家族に必要な支援が届くことを願っています。








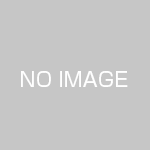





この記事へのコメントはありません。