
epa介護問題点に、あなたはもう気づいていますか?
epa介護問題点――この言葉に、なんとなくモヤモヤするものを感じたことはありませんか?
「外国人介護士が入ってきたけど、長続きしない」「制度はあるのに、うまく機能していない気がする」。
そんな違和感を、あなたの職場でも感じていないでしょうか。
制度自体は、“国と国の約束”として立派に整っています。
でも、いざ現場で働くEPA介護士本人や、受け入れる側の介護施設にとっては、その制度が“壁”にもなってしまっている。
そういう構造的なズレが、今も多くの混乱を生んでいるのです。
この記事では、その「文化・制度・意識のチグハグ」がなぜ起きてしまうのか。
そして、それをどう乗り越えればいいのかを、一緒に見ていきましょう。
Contents
制度は整っているのに…epa介護問題点の本質とは?
“学ぶ制度”なのに“働ける人材”として期待される
EPA制度は、外国人介護士が日本で学び、介護福祉士の資格取得を目指すためのものです。
けれど、現場の本音は「即戦力がほしい」。
このギャップが、epa介護問題点の大きなひとつです。
実際、来日後すぐにシフトに組み込まれ、資格も取っていないのに重度の介助を任されるケースもあるほどです。
本来なら「学ぶ」ことが第一なのに、いきなり“戦力”を求められる――そのプレッシャーと現実の乖離が、EPA介護士たちのストレスや離脱の原因になっているのです。
文化・価値観の違いに寄り添う体制が弱い
介護は、単なる作業ではありません。
日本独特の「察する介護」「相手の気持ちを先読みする文化」が根底にあります。
けれど、EPA介護士にとっては、それが非常に曖昧で理解しにくい部分でもあります。
さらに、国によっては異性介助が禁忌であったり、家族介護が基本だったりと、文化的背景も大きく異なります。
その中で「なんでできないの?」と責められると、彼らは深く傷ついてしまいます。
epa介護問題点が“構造的欠陥”になっている理由
国家試験制度が“定着”ではなく“帰国”を生む
制度上、EPA介護士は一定期間内に国家試験に合格しなければ帰国しなければなりません。
この「一発勝負」の仕組みは、想像以上に彼らのプレッシャーになっています。
さらに、合格したとしても、処遇が劇的に良くなるとは限らない。
「試験のために働いて、試験が終わったら戻る」というロジックが自然にできてしまい、制度が定着支援ではなく、結果的に“短期滞在モデル”になってしまっているのです。
受け入れ施設側も疲弊している
epa介護問題点は、外国人側だけの問題ではありません。
受け入れ施設の側も、言語サポート・文化理解・試験対策など、通常業務とは別のタスクを抱え込むことになります。
しかも、教えた人材が国家試験不合格で帰国してしまうと、投資した時間やコストも無駄になってしまうという喪失感までついてくるのです。
それが、「もうEPAはやめておこう…」という流れにつながってしまっています。
では、どうすれば?“チグハグ”を解消する3つのヒント
①制度を“教育型”ではなく“伴走型”に見直す
まずは制度設計の見直しが必要です。
国家試験合格がゴールではなく、「実践しながら成長できる」モデルへの転換が求められます。
たとえば段階的なスキル認定制度、合格までの猶予期間の延長、または資格以外の在留継続ルートの導入など、柔軟な制度があれば、多くのEPA介護士が安心して働けるようになります。
②“多文化理解”を組織に根づかせる
現場の一人ひとりが、EPA介護士を「異文化の人」としてではなく、「同じチームの一員」として受け入れるためには、継続的な学びが欠かせません。
月1回の文化交流タイムや、失敗談を共有するミーティングなど、カジュアルな取り組みを日常の中に組み込んでいくことで、誤解は確実に減っていきます。
③EPA介護士の“未来設計”を一緒に描く
「ここで働き続けたらどうなるか?」
EPA介護士自身にその未来が見えていなければ、帰国を選ぶのは当然です。
職場側が一緒にキャリアプランを考え、資格取得後の待遇やキャリアパス、永住支援の道を提示できれば、彼らの“働く意味”は大きく変わります。
まとめ:epa介護問題点の解決は、“共に育つ”姿勢から
epa介護問題点の本質は、文化・制度・意識――この3つの歯車がうまくかみ合っていないことにあります。
でも、そのチグハグは、仕組みと心の両方を少しずつ変えていけば、必ず埋められる溝です。
あなたの現場にいるEPA介護士も、きっと不安や希望を抱えて日々頑張っているはずです。
その努力を「戦力」として見るだけでなく、「仲間」として育てる視点を持つこと。
それが、これからの介護現場に求められる“本当の国際共生”ではないでしょうか。












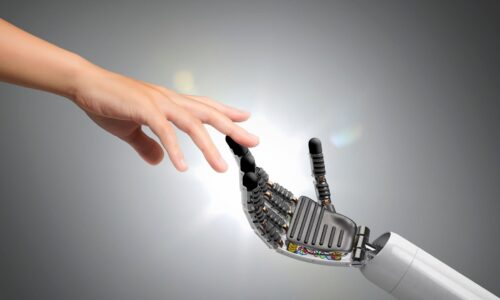

この記事へのコメントはありません。